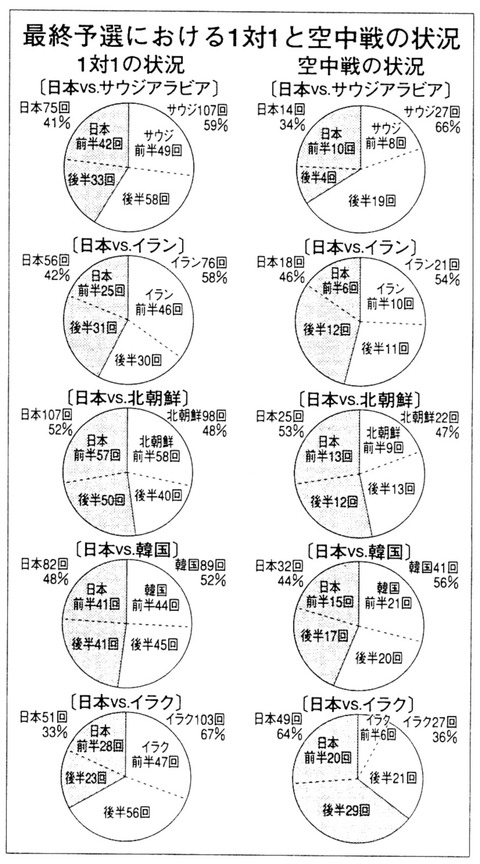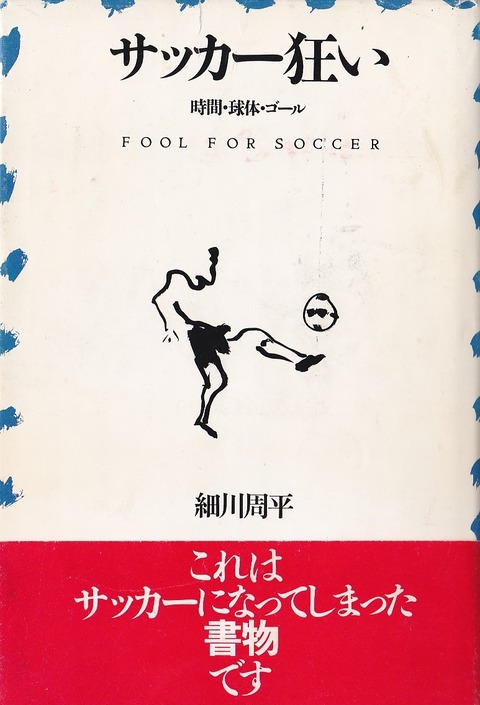『サッカー狂い』への過剰な評価
日本のサッカー界隈では、細川周平氏(音楽学者,フランス現代思想家)の著作『サッカー狂い~時間・球体・ゴール』(1989年)がカリスマ本扱いされている。
ドゥルーズ=ガタリをはじめとしたフランス現代思想を援用しつつ、「サッカーそのもの」の美やサッカーへの愛を語った名著として過剰なまでに高く評価されてきた。
しかし、ハッキリ言ってそこまで賛美するほどの著作ではない。千野圭一編集長時代の旧「WEBサッカーマガジン」の匿名電子掲示板に、この本のことを「サッカー冷遇時代におけるヒガミ根性丸出しの一冊」と揶揄した書き込みがあったが、この指摘はある意味で正しい。
そうした性格をキチンと知らないことには『サッカー狂い』の評価をかえって誤るし、日本のサッカー文化総体も理解できない。
ニューアカとスポーツ評論
そもそもJリーグが始まる1993年より4年も前、後藤健生氏の『サッカーの世紀』が刊行された1995年より6年も前の1989年「日本サッカー冬の時代」に、何故このような本が出版できたのか?
まず時代背景がある。1980年代、いわゆる「ニューアカデミズム」が持てはやされており、フランス現代思想、ポストモダン哲学、ポスト構造主義……といった知的潮流が輸入され、一種のファッションとして流行していた。細川周平氏も、音楽学者として『音楽の記号論』や『ウォークマンの修辞学』その他の論考で、ニューアカ・ブームの一翼を担っていた。
ニューアカからのスポーツへの言及としては、文芸・映画評論家の蓮實重彦氏(時に「草野進」名義も使用)らが行った、大胆で放埓な修辞と晦渋な文体、そして「スポーツそのものの美こそが絶対」という視点に立った「プロ野球批評」がこれまた称揚されていた。
細川周平氏が『サッカー狂い』を執筆し、上梓することができたのは、そうした時代の余恵にあずかったところが大きい。
狭い内輪の世界の「お作法」
しかし、細川周平氏や蓮實重彦氏が依ってきたフランス現代思想というものは、いたずらに晦渋なだけで、世の中の実際の在り様に真摯に対応していない「絵空事」であると、しばしば批判されてきた代物でもある。
だから、フランス現代思想やそれに触発された文芸批評に乗じたスポーツ「批評」というのは、あくまで狭い内輪の世界の「お作法」でしかない。スポーツ評論ではなく、いわばスポーツの文芸批評であり、あるいはスポーツを種にしたフランス現代思想の展開にすぎない。
この種の思想に没入し、特定の対象を耽溺するようになると、その対象の外にあるものは強迫的に嫌悪するようになる。『サッカー狂い』も同様。例えば、野球、ラグビー、アメリカンフットボール(著者・細川氏は蔑称のように「アメラグ」=アメリカンラグビーの略=と呼ぶ)といった他の球技スポーツへの悪罵である。
しかし、それぞれのスポーツは各々固有のゲーム性=面白さが当然あるわけだから、細川周平氏の言説はいかにも品がない。
日本サッカー界隈における反ドイツ主義
あるいは、著者が考える「サッカーならざるもの」への憎しみは、同じサッカーの中にも及ぶ。ドイツのサッカーを勝利至上主義の権化「愚鈍なサッカー」として執拗に嫌悪し出したのも『サッカー狂い』である。以来、日本のサッカー界隈はドイツ・サッカーに対する好感を素直に表明しづらくなった。
たしかに、橋本誠記者(時事通信社)もまた、時事通信社のWEBサイトで、もともと親ドイツだった日本サッカー界の反動としての、日本人サッカーファンのドイツ・サッカーへの複雑な感情を書き連ねてはいる。
- 参照:橋本誠「だからサッカー・ドイツ代表が嫌いだった~最強チームへの敬意を込めて」https://www.jiji.com/sp/v4?id=germannationalfb0001
だが、それと比べても細川周平氏の言説はいかにも品がない。
サッカーは「反日本的」か?
さらに、細川周平氏の嫌悪の矛先は、まだ「冬の時代」だった日本サッカーにも及ぶ。
とにかく折に触れては日本のサッカーを執拗なまでに貶し、卑下する。著者曰く「サッカーを愛すれば愛するほど、ぼく〔細川周平氏〕は日本から遠ざかっていく気がする。サッカーはもしかすると反日本的な競技なのかもしれない」……と。
しかし、その自虐的な日本サッカー観の根底にあるのは何かといえば、サッカーは狩猟民族のスポーツで日本人は農耕民族なのだからサッカーに向いていない……といった類の陳腐で凡庸で、そして決定的に間違っている日本人論・日本文化論的サッカー観である。
細川周平氏の言説はいかにも品がない。
日本の「サッカー狂い」の分断
これら全て著者の「ヒガミ根性」なのだが、それをフランス現代思想のファッショナブルな衒学で飾っているだけに非常に厄介である。細川周平氏の『サッカー狂い』は「この本は知的に高尚で深遠であるはず」「自分は頭が悪いとは思われたくない」と自らに強迫した日本のサッカーファンによって正当化され、称揚されてきた。
それは「日本サッカー冬の時代」の限界だろうか? その認識が正しくないのは、例えば日本サッカー狂会の鈴木良韶和尚や、久保田淳氏(著書に『ぼくたちのW杯~サポーターが見た!フランスへの熱き軌跡』ほか)、後藤健生氏(著書に『日本サッカーの未来世紀』ほか)のように、Jリーグ以前から、苦い肝を嘗めながらも日本サッカーを見捨てずに応援してきた「サッカー狂い」の層が一方で存在するからである。
細川周平氏に象徴されるサッカー狂、翻って鈴木和尚や久保田氏、後藤氏に代表されるサッカー狂。このふたつの日本のサッカーファン層の間には高くて長い壁が存在している。
『サッカー狂い』は、はしたなくも日本のサッカーの精神文化を表している。後の時代の金子達仁氏や杉山茂樹氏、村上龍氏……といった、日本サッカーを殊更に蔑んでは自身のサッカー観の確かさや批評精神を誇示するサッカー関係者の先駆けと言える。
また、日本のサッカーを敬遠するが欧州の一流どころの海外サッカーは嗜むサッカーファン層(むろん細川周平氏は日本のサッカーとドイツ以外の海外のサッカーとサッカー文化には好意的である)と、日本代表やJリーグなど日本サッカーを応援するサッカーファン層との分断の先駆けとも言える。
どうしたって『サッカー狂い』は面白く読めない。けれども日本のサッカーやサッカーファンの屈折した精神史を、著者・細川周平氏の意図とは違った視点で興味深くたどれるトンデモない史料(資料)としては、反比例的な評価はできるのかもしれない。
(了)

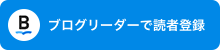

続きを読む