書評とブックガイドの専門月刊誌『本の雑誌』、2022年4月号の特集は「スポーツ本の春!」で、その目玉が座談会「スポーツ本オールタイムベスト50が決定!」であった。
- 参照:『本の雑誌』2022年4月号(特集 スポーツ本の春!)https://www.webdoku.jp/honshi/2022/4-220303152432.html
野球、サッカー、格闘技、陸上競技……。ところが、驚いたのはこのベスト50の中に「ラグビー」の本が入っていなかったことである。しかも、記事にも言及がなかった。
これには「日本ラグビー狂会」を名乗るラグビー評論家の中尾亘孝(なかお のぶたか)<1>も不満だったようだ(次のツイート参照)。
gazinsai@gazinsai
>月例の駅前新刊本屋で「#本の雑誌」4月号、
2022/03/21 18:37:42
>「本の雑誌」がスポーツ本の特集なのに、
>「ベスト50」はおろか、記事にもラグビー本の言及なし。
>う~~む、#ラグビー のラの字もない、
>これには言葉を失う。
往年のラグビ… https://t.co/AbAyVWMzL7
なぜ驚いたかというと、ラグビーは、日本のスポーツ界において歴史的にも一定のステータスを誇ってきたからだ。Jリーグ(1993年~)以前はサッカーよりも人気があったくらいだし、ラグビー関連書籍も良書が沢山あったからだ。
文春ナンバーは、ラグビーブームにあった1980年代、盛んにラグビー特集を組んだ……。
- 参照:Sports Graphic Number 88号 ラグビー・男の季節(1983年11月19日発売)https://number.bunshun.jp/articles/-/454
2019年には、日本でラグビーW杯を開催、大変な盛況だった……。
……にもかかわらず、『本の雑誌』のスポーツ本特集にラグビー本がなかったのである。
大西鐵之祐(おおにし てつのすけ)の『闘争の論理』。そして……。
藤島大の『知と熱』くらいはベスト50に入ってもよさそうなものを。
確かにこれは解せない。
☆★☆★☆★☆★
要は、日本は長らく野球の国だった(過去形)ので、『本の雑誌』あたりがスポーツ本ベストの特集を組むと、どうしても野球の本が多くなる。加えてサッカーが台頭してきたりすると、サッカー本も多くなり、ラグビー本は省かれてしまう……のかもしれない。
その分、例えば省かれたラグビーファンからは不満が出る。
これに比べると、本邦スポーツライティングの「傑作スポーツアンソロジー」を編むのに、野球(『9回裏2死満塁』)と、それ以外のスポーツ(『彼らの奇蹟』)とを分けて刊行した……。
……玉木正之氏と新潮社はずいぶん賢明な判断をしたと思う。
(了)

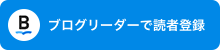

続きを読む















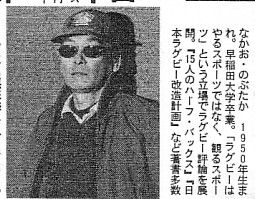



![NHK特集 江夏の21球 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/5128yZ9CqxL._SL160_.jpg)











