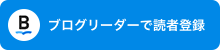中田英寿にまつわる仰天エピソード
2020年2月3日、ヤフー!ジャパンが、Goal.comからの配信として「トッティ氏,仰天エピソードに中田英寿氏を選出〈なぜそんなことを.彼は本当に特別な人〉」なる、サッカー元イタリア代表フランチェスコ・トッティのインタビュー記事を公開した。
- トッティ氏、仰天エピソードに中田英寿氏を選出「なぜそんなことを.彼は本当に特別な人」
彼とサッカー元日本代表・中田英寿は、かつてイタリア・セリエAの名門ASローマでチームメイトであった。ASローマは、2000-2001シーズンにセリエAで18シーズンぶりに優勝した。
その快挙、ASローマの選手やスタッフたちによる歓喜の輪の中にあって、中田英寿だけは「優勝が決まった直後,ロッカールームの隅で読書をしていた」という逸話を、トッティは「現役時代を通じ,最も驚いた仰天エピソード」として紹介している。
「私〔トッティ〕は〔現役時代を通じ,最も驚いた仰天エピソードとして〕ナカタ〔中田英寿〕を選ぶ。なぜならナカタは、スクデットのお祭り騒ぎの中、本当に読書していたんだよ。なぜそんなことをしていたのかは分からない。彼〔中田英寿〕は本当に特別な人だよ」Goal.comより
この珍記事を受けて、中田英寿を素朴に信奉する、いたいけな人たちの反応がSNSやヤフー!ジャパンのコメント欄に現れている。以下は、そのマンセ~、ハラショ~のほんの一例であるが……。
ryo_6556@ryo_6556
トッティ氏、仰天エピソードに中田英寿氏を選出「なぜそんなことを。彼は本当に特別な人」 https://t.co/oQqikAg0rk
2020/02/04 11:28:02
水野祐 CITY LIGHTS LAW🙊@TasukuMizuno
こうやって語られることがすごい。
2020/02/03 23:23:07
トッティ氏、仰天エピソードに中田英寿氏を選出「なぜそんなことを。彼は本当に特別な人」 https://t.co/VLeDRcFqmd
まえもん⊿ 京セラ② ヤフオク@mae_mon
二人の思わぬ友情エピソードかと思ったがちょっと違ったw
2020/02/08 00:12:11
でも真っ先にヒデの名前出るのはすごいね。
トッティ氏、仰天エピソードに中田英寿氏を選出「なぜそんなことを。彼は本当に特別な人」(GOAL) https://t.co/t1p3uR6Zzk
……なるほど。「中田英寿神話」はこうやってメンテナンスされていくのだ。
英国における「大卒」サッカー選手の苦悩
読めば分かるのだが、トッティは、あくまで「現役時代を通じ,最も驚いた仰天エピソード」を語ったのであって、「現役時代を通じ,最も驚いたサッカー選手やそのプレー」を語ったわけではない。
該当記事を読む限り、トッティは中田英寿をそのように評価したわけではない。
この「仰天エピソード」を読んで、むしろ、思い出したことがある。サッカーとサッカーカルチャーのことならおおよその事柄が書いてある、デズモンド・モリス博士の『サッカー人間学』(1983年,原題:The Soccer Tribe)に登場する話だ。
英国イングランドのプロサッカー選手で、数少ない「大学卒」のインテリだったリバプールFCのスティーブ・ハイウェイ(Steve Heighway,1947年生まれ,ウォーリック大学卒)の「苦悩」である。
大学教育まで受けた数少ない一流選手の一人で、リバプールで活躍するスティーブ・ハイウェイには,このような〔低学歴のプロサッカー〕選手〔たち〕の態度は大変な驚きであった。リバプール・チームに入った当初,彼〔ハイウェイ〕は相手チームと対戦する時と同じように,自チームの仲間との交際が怖かったという。あるスポーツ解説者は「彼はこの社会〔プロサッカー選手たちの世界〕の不適応者だった」といい,「遠征先でトランプ〔≒少額の賭け事〕が始まると,ハイウェイは抜け出して観光団に加わった。仲間には,明らかにインテリを鼻にかけた生意気な態度と映った。彼が戻ると,みんなは威嚇〔いかく〕的な視線を送って,トランプに仲間入りする気があるかどうか尋ねた」と伝えている。ハイウェイは変人扱いを受けるのがたまらず,何とか順応しようとした。デズモンド・モリス『サッカー人間学』183頁
チームの雰囲気に馴染めなかったという意味では、スティーブ・ハイウェイと中田英寿は、ある意味で似ている(まだハイウェイはチームに馴染もうとしていたのだが)。
サッカー選手は「ハマータウンの野郎ども」である!?
デズモンド・モリスが『サッカー人間学』で描き出した、プロサッカー選手のイメージ(ステレオタイプ)を抄出してみると……。
- 芸術や科学や政治に関心がなく、サッカーにしか興味がない。
- 暇な時、特に遠征時の移動中は、トランプのゲーム≒少額の賭け事を楽しんでいる。
- 映画やテレビをよく見るが、(高尚な作品ではなく)スリラーやアクションが多い。
- 読書も、サッカー関係の雑誌か、タブロイド紙の推理小説やスリラーの域を出ない。
- 挑発的で威圧的なキャラクターの女性は好まれない。
- 好きな音楽はロックやポップに限られている(クラシックではない)。
- 遠征先の有名な観光地の見学には興味が薄く、つまりは知的好奇心に乏しい。
……等々。ものの見事にサッカー馬鹿であり、粗にして野であり、けして「知的」とはいえない。これでは、スティーブ・ハイウェイが馴染めないのは当然だ。
これには、英国という社会のしくみが絡んでいる。いわゆる「階級社会」である。例えば、単純な計算で、英国の大学の数は日本の4割程度しかない。しかも進学率が低い。
英国の子供は11歳(!)で学力試験を受けて、そのうち所定の成績を上げた3割程度しか高等教育の学校(大学など)に進学できない。残り7割のほとんどはステートスクール(公立中学)を卒業したら、そのまま労働者として社会に出る(この段落の知識は,林信吾『これが英国労働党だ』によるもの)。
現在の英国でも、欧州の他の国も、おおむね事情は似たようなものである。
サッカー選手は、労働者階級のスポーツである。選手の出身も労働者階級が多い。
すなわち、サッカー選手は、なかんずくプロサッカー選手は。大学に進学するような知的エリート≒上流階級(的な人)がやるスポーツだとは思われていない。そして、選手の言動や立ち振る舞いも労働者階級的であることを求められる。
世の中には知的ならざる、しかしそれなしでは社会が動かない人たちの分厚い層があるのだという単純な事実……。知性をバカにすることによってプライドを保つ人たちが、そしてそういう人によってしか担われない領域の仕事というものがこの世には存在するのである。〔英国の〕社会学者ポール・ウィリスはその辺の事情を見事に明らかにしている〔ポール・ウィリスの著作『ハマータウンの野郎ども』のこと〕。
世の中は……知的エリートによってだけ動いているのではない。……知的であることによってプライドを充足できる。他方に反知性によりプライドを充足する人々がいる。人間はプライドなしには生きられないという観点からすれば、どちらも等価である。三浦淳「捕鯨の病理学(第4回)」http://luna.pos.to/whale/jpn_nemo6.html
すなわち、プロサッカーとは「知的ならざる,しかしそれなしでは社会が動かない人たちの分厚い層」あるいは「反知性によりプライドを充足する人々の」ための、基本的に「そういう人によってしか担われない領域の仕事」なのである。
サッカー選手たちとは、とどのつまり「ハマータウンの野郎ども」なのだ。
スティーブ・ハイウェイの「苦悩」の背景がここにある。「大学卒業」の学歴を持つハイウェイが馴染めないのは、プロサッカーが「労働者階級」の社会だからである。
「体育会系」という反知性的なコミュニティ
その昔、1960年代、サッカー日本代表がヨーロッパに遠征した。そのスコッドの選手たちは、大学生や大学卒業の選手がほとんどだった。例えば、杉山隆一は明治大学卒業、釜本邦茂は早稲田大学卒業である。
そのため、学歴のないサッカー選手が多いヨーロッパの現地では、珍しく受け取られたという。
だからと言って、日本のサッカー選手やアスリートが、真に「知的」かどうかは微妙である。
日本の大学スポーツの体育会・運動部には「体育会系」という言葉(概念)があり、それは「体育会の運動部などで重視される,目上の者への服従や根性論などを尊ぶ気質.また,そのような気質が濃厚な人や組織」(デジタル大辞泉)と解釈される。
すなわち、あまり「知的」とは見なされない。日本においてもサッカーを含むスポーツ選手は、あまり賢くないというイメージ(ステレオタイプ)があり、当事者もそこに充足しきっているというところがある。
洋の東西を問わず、サッカー選手は敢えて「知的」でないことを誇っている節がある。
そういえば、フランチェスコ・トッティは「知的」ではなく「間の抜けた男の愛嬌」を感じさせる逸話が多い。日本で言えば、プロ野球の長嶋茂雄のそれに通じるものがある。
対して、中田英寿の逸話は対照的である。世界最高峰のサッカーリーグであるセリエAで優勝したにもかかわらず、ひとり「ロッカールームの隅で読書をしていた」というのは、そうしたサッカー界の風潮には順応できなかった……ということである。
中田英寿は「真に知的なアスリート」なのか?
所詮、スポーツなど馬鹿がやる仕事なのか? 否。スポーツライターの藤島大は、スポーツこそ「知的」な営為であると説き、中田英寿のような安易なアンチテーゼ的振る舞いの方を批判している(下記リンク先参照)。曰く……。
スポーツとは、そもそも高等な営みである。一流選手が経験する真剣勝負の場では、緊急事態における感情や知性のコントロールを要求される。へばって疲れてなお人間らしく振る舞う。最良の選択を試みる。この訓練は、きっと戦争とスポーツでしかできない。だからアスリートは、机上では得られぬ知性をピッチやフィールドの内外に表現しなければならない。常識あるスポーツ人が、非日常の修羅場でつかんだ実感を、経営コンサルタントや自己啓発セミナーもどきの紙切れの能弁ではなく、本物の「詩」で表現する。そんな時代の到来を待ちたい。「片田舎の青年が、おのれを知り、世界を知り、やがて、おのれに帰る。だからラグビーは素敵なのだ」かつてのフランス代表のプロップ、ピエール・ドスピタルの名言である。バスク民謡の歌手でもある臼のごとき大男は、愛する競技の魅力を断言してみせたのだ。
……たしかにドスピタルの言葉に比べると、中田英寿の『中田語録』などは「机上の知性」あるいは「紙切れの能弁」でしかない。
知的とは思われていないフットボーラーだが、フットボールを極めると、むしろ、だからこそ真に知的な言葉が出てくる。一見すると、矛盾している。矛盾しているが、真理である。
その真理を、ついに理解できなかったのが中田英寿である。
中田英寿から透けて見える日本サッカー界の「知性」
藤島大が「真に知的なアスリートの到来」を期待したのは、2001年1月のことである。
あれから、20年近くたった2020年2月。しかし、未だに「中田英寿の仰天エピソード」が出てくる。未だに「中田英寿神話」のメンテナンスが行われる……。
……ということは、日本サッカー界の知的レベルが更新されていないということでなる。
中田英寿は「サッカー馬鹿」になるべき時になれない体質だった。そこにサッカー選手として才能の限界があった。中田英寿は、だから、ワールドクラスのサッカー選手としてのキャリアを形成できたわけではない。
代わりに、中田英寿は、日本のサッカー界の知性の低劣さを巧妙に刺激する才能には長(た)けている。2000年のアウェー国際試合「フランスvs日本」戦のパフォーマンスなどは、そうである。
そこで錯覚してしまう、いたいけな日本人が多い。残念でならない。
中田英寿は「特別な人」ではなく「特殊な人」である
ところで、くだんのトッティのインタビュー記事。イタリア語原文がどうなっていたのかは分からないが、日本語の翻訳をちょっとだけ改変してみると、がぜん面白くなる。
- トッティ「なぜそんなことを.彼〔中田英寿〕は本当に特別な人」
ここから単語をひとつ置換してみる。
- トッティ「なぜそんなことを.彼〔中田英寿〕は本当に特殊な人」
フランチェスコ・トッティが「なぜそんなことをしていたのかは分からない」というくらいだから、後者の方がニュアンスが通じる!?
ことほど左様、日本にとっても、国際的にも、中田英寿は「特別なサッカー人」ではない「特殊なサッカー人」なのである。
こちらの方が、中田英寿という人間の本質を言い当てている。
(了)
続きを読む