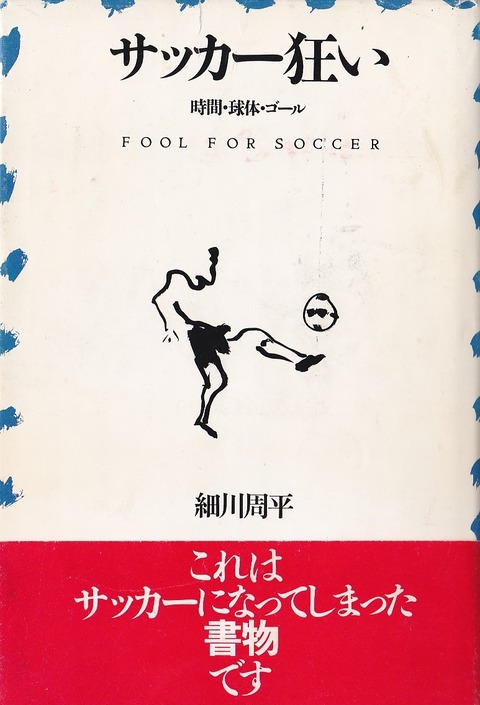守田英正選手の悲痛なコメント
2024年1~2月にカタールで行われた「アジアカップ2023」、サッカー日本代表=森保ジャパンは「日本サッカー史上最強」と呼ばれ、優勝を期待されながら、しかし準々決勝(ベスト8)で敗退してしまった。これには多くのサッカーファンの失望している。
日本が敗れた対イラン戦は、後半、日本が防戦一方になりながら(そして後半終了直前に与えたPKを決められた)、森保一監督は選手交代や守備の指示など、何の手も打たなかった。この森保采配についても多くのサッカーファンの失望している。
これには選手、例えば守田英正選手からも異論が出ている。
……後半10分に追いつかれてから我慢の時間が続き、後半アディショナルタイムにPKで決勝点を献上。そんな試合展開に守田〔英正〕は偽らざる胸中を吐露した。「どうすれば良かったのかはハッキリ分からない。考えすぎてパンクというか、もっとアドバイスとか、外からこうした方がいいとか、チームとしてこういうことを徹底しようとかと〔ベンチからの声〕が欲しい。チームとしての徹底度が足りなくて試合展開を握られるということがゼロじゃないし、この大会でも少なからずあった。ボランチとして、プレイヤーとして、チームのために考えないといけないし、その思考は止めないけど、そこの決定権が僕にある必要はないのかなと思う。あくまで僕は最後の微調整だけでいいのかなと。担っているものを重荷には感じないけど、もっと〔ベンチからのアドバイスが〕欲しい」ピッチ上の選手だけで対応するのにも限界がある。劣勢の展開の中でもっとベンチからの明確な指示があっても良かったのではないか。〔以下略〕西山紘平/ゲキサカ「苦悩を吐露した守田英正の悲痛な叫び〈考えすぎてパンク〉〈もっといろいろ提示してほしい〉」(2024/2/4)https://web.gekisaka.jp/news/japan/detail/?400971-400971-fl
一方、これについては、次のような解釈も存在する。
守田〔英正〕は今回の発言の際、非常に言葉を選びながら絞り出すように思いを口にしていたが、森保一監督を始めベンチ側から「もっと提示して欲しい」というのはこれまでもよく話題に上がっていたこと。〔略〕ただ一方で、そういった状況を分かった上で指揮官が〈動かない〉ことを選択している節もある。〔略〕目の前の勝利とともに日本サッカーの発展を考えるが故に、何もしないことで選手たちがどう反応し、どういった解決を図るかを見守っているところがある。そこは森保監督の〈ズルさ〉と表現していい。林遼平/GOAL「なぜ優勝にたどりつけなかったのか.アジア杯を戦う日本代表にあった2つの〈問題〉」(2024年2月08日)https://www.goal.com/jp/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9/japan-asian-cup-review-20240208/blt495228c8f255efbc
それにしても、2024年の今でもこういう奇妙な論理が出てくるのか? ……と(当ブログは)驚く。
まず、アジアカップの準々決勝はあえて「〈動かない〉ことを選択」して勝たなくてももいいという試合ではなく、何が何でも勝ちにいかなければならない試合である。
何より、森保一監督はあえて「〈動かない〉ことを選択」した、「ズルさ」の現れなのではなく、試合中、単純にフリーズしてしまい、適切な手が打てなかったのではないか……という批判的な指摘の方が多数派である。
日本のスポーツ界と「ボトムアップ型」の日本代表
森保一監督はチームに戦術の仕込みをせず、試合中、選手たちに具体的な指示を送ることも少ない。これを「ボトムアップ型」の監督と呼ばれるが、別の(悪い)言い方をすると「戦術やプレーを選手たちに丸投げ」する監督ということである。
木村浩嗣氏(元フットボリスタ誌編集長)が、小澤一郎氏(サッカージャーナリスト)が主宰するYouTube番組の中で「ボトムアップ型の監督やチームなんてスペインサッカーじゃ有り得ない!!」と語っていたが、なぜ日本にそのような類型が存在するのか?
[冒頭10分公開]スペインから見た日本代表の弱点と敗因。「監督で負けた」「ボトムアップなんてありえない」
日本のスポーツ界、日本のスポーツ論壇には、「〈日本人〉のスポーツ選手は細かい戦術指導や指示をすると思考の柔軟性を失い、その枠をはみ出てプレーをすることが出来なくなる」という「迷信」がある。特にサッカーやラグビーなどはそう言われる。
だから、それを乗り越えるため……と称して、日本のスポーツ界は「ボトムアップ型」の日本代表が時として登場してきた。すなわち、1997年~2000年のラグビー日本代表「平尾ジャパン」、2002年~2006年のサッカー日本代表「ジーコ・ジャパン」がそうである。
平尾ジャパンの平尾誠二監督(故人)は、次のように述べている。
「多様な局面に対し、多様に瞬時に対応できるのが、現代のいいプレーヤーの条件です。しかし、これは日本人が一番弱い部分。そもそも、そういう教育がされていない」「(ラグビーのゲームは)常に状況が変わり、選手がどうカオス(混とん)に対応するかが問題になる」『日本経済新聞』1999年11月20日付
今でこそ、森保ジャパンを鋭く批判している西部謙司氏(サッカー記者)であるが、かつてはこの論理でジーコ・ジャパン(セレクター型監督と称していた)の熱烈な支持者であった。森保一監督は「セレクター型」の監督なのだろうか?
前掲の林遼平氏(GOAL.COM)の言い分は、実はこの論理をなぞったものである。
「日本人」と「自己決定力」
そもそも、森保一監督の「雇い主」であるところの田嶋幸三JFA会長(2024年3月で退任予定)自身が、そういう「迷信」を信じているのではないか? ……との見方がある。田嶋幸三会長の著作、2007年に出た『「言語技術」が日本のサッカーを変える』の冒頭にはこうある。<1>
2007年1月、大坂で「第5回フットボールカンファレンス」が開催されました。メインテーマは、06年にドイツで開催されたワールドカップの分析と報告です。このカンファレンスで私〔田嶋幸三〕は「日本代表報告」を担当することになっていました。私が壇上に立つ直前、ハッとするような話が耳に飛び込んできたのです。ワールドカップの準決勝・イタリア対ドイツ――この大会で何試合かアシスタントレフェリーを務めていた廣嶋禎数〔ひろしま・よしかず〕さんが、こんな話を始めました。「イタリアの選手が退場させられて選手が1人減ってしまったその時、イタリアの選手たちは、誰1人として、ベンチを見なかった」イタリア・チーム〔2006年ドイツW杯で優勝〕は、状況からして非常に不利な局面を迎えていた。にもかかわらず、選手たちはベンチに指示を仰がなかった。その場で話し合いをはじめ、10人でどのように試合を進めていくのかを即座に決め、お互いに指示を出し合い、発生した問題を解決していった――というのです。ピッチ上の選手が、「ベンチを見ない」。そのことは、いったい何を示しているのでしょうか? サッカーにとって、どれくらい重要な意味があるのでしょうか?イタリアのメンバーたちは、選手が1人欠けてしまった場面に遭遇しても、自分たちで判断し難問を解決する力を持っていました。そうした能力をしっかり養ってきたからこそ、彼らはベンチに対して「指示を求めなかった」のです。つまり、「ベンチを見ない」ということは、ピッチ上で発生した出来事をどう処理していくのか、そのために分析力と判断力を発揮して、決定する「力」を持っていたことの「証」〔あかし〕でした。究極の状況下で、自ら考えて判断を下す「自己決定力」。その力を備えていない限り、世界で通用するサッカー選手になることはできない、という事実を明確に示している――そうした出来事だと、私〔田嶋幸三〕には思えたのでした。でははたして、日本の選手たちはどうでしょう?日本のサッカーは、どれくらい「自己決定力」の大切さを意識してきたでしょうか? そうした能力を養っていくための訓練をしてきたでしょうか? 学校や家庭で、そうした能力を育む努力や工夫を、重ねてきたでしょうか? 「自己決定力」を支える、論理や表現力を学ぶシステムは、確立されているでしょうか? それともそうしたことの大切さすら、まだ自覚されていないのでしょうか?田嶋幸三「ベンチを見ないイタリア・チーム」@『「言語技術」が日本のサッカーを変える』7頁~9頁
平尾誠二監督と田嶋幸三会長の「日本人観」は、非常によく似ている。そして、ジーコ・ジャパン(や平尾ジャパン)の擁護論として、多用された言い回しでもあった。
ジーコ・ジャパンは(平尾ジャパンも)、肝心なワールドカップ本大会では惨敗した。しかし、それは田嶋幸三会長が述べるところの「日本人の〈自己決定力〉の欠如」の問題であって、ジーコ・ジャパンの監督であるジーコ氏の責任ではない……ということで片付けられてしまった。
この度の守田英正選手のコメントは、彼がサッカー選手としてレベルが低いということの「証」なのだろうか? ……それは違う。
「迷信」に斬り込んだスポーツライター
藤島大氏(スポーツライター)は、あるいは大西鐵之祐氏(ラグビー日本代表監督ほか)の薫陶を受けたためもあるのかもしれない。「ボトムアップ型」日本代表を生み出す、日本スポーツ界の「迷信」を批判してきた。
なぜかスポーツとなると「型」〔≒指示、戦術〕と「個性」〔≒自己決定力〕の対極へと位置づけるナイーブな論調が跋扈〔ばっこ〕する。しかし、マイク・タイソン〔元プロボクシング世界ヘビー級チャンピオン〕は厳しいパターンに従って戦ったプロデビュー直後こそ、もっともタイソンらしかった。〔略〕つまりスポーツに型はあるものなのだ。そして型を実行する過程においても「その人らしさ」は必ず反映されるし、「ここに拠点ができたら必ず右に攻めろ」とパターン化しても、パスをするのか蹴るのか当たるのかは「個人の判断」がしばしば決定する。藤島大「〈史上最強〉の虚実」@『ラグビーの世紀』104頁
型、パターン、戦術を明快に打ち立てると、個人の判断や力強さが身につかない。とらわれがちな呪縛〔じゅばく〕ではある。少年期なら自由な判断と一般的な基本技術がとことん尊重されるべきだ。しかし〔日本〕代表の具体的なチーム作りにあっては、それでは時間が足りなくなる。それに、一級の指導者は選手の個性を観察した後にふさわしい型を構築するものなのだ。藤島大「〈史上最強〉の虚実」@『ラグビーの世紀』106頁
以上、平尾ジャパンを総括した記事である。実に溜飲が下がる。聞いているか!? 田嶋幸三会長! そして宮本恒靖次期JFA会長! ……と言いたくなる。
藤島大氏は該当記事で、松尾雄治氏(元ラグビー日本代表)から「戦争に行ってさ、個人の判断でいけ、なんて嫌だよ。そんなの。あっちこっちに勝手に弾打ってさ。そんなんで、どうして死ねるんだよ」という、平尾ジャパンをやんわり批判した比喩的なコメントを引き出している。
守田英正選手のコメント(あるいは三笘薫選手のコメント)は「そんなんで、どうして死ねるんだよ」という気持ちの表明でもあったのかもしれない。
藤島大氏の筆鋒は、ジーコ・ジャパンの総括にも向けられている。
ジーコが悪い。ジーコがしくじったから〔サッカー日本代表は2006年ドイツW杯で〕負けた。なぜか。チャンピオンシップのスポーツにおいて敗北の責任は、絶対にコーチ〔監督〕にあるからだ。〔略〕シュートの不得手なFW〔柳沢敦〕を選んで、緻密な戦法抜きの荒野に放り出して、シュートを外したと選んだコーチ〔監督〕が非難したらアンフェアだ。藤島大「ジーコのせいだ」(2006年7月27日)https://www.suzukirugby.com/column/column984
柳沢敦のQBK:急に(Q)ボールが(B)来たので(K)
サッカージャーナリストの多くが「迷信」の前にジーコを批判できず、沈黙してしまったのに対し、まことに胸のすく啖呵である。
あの対イラン戦。ロングボールをゴール前に放り込まれ続けられる「荒野」の中で、しかし、しかるべき守備の指示もなく、なすがままに敗れ去ってしまったのが森保ジャパンだった。
サッカーはアップデートしている
もうひとつ。そもそも、イタリア代表の選手たちがW杯の準決勝でピンチに陥ってもベンチ(監督)の指示を仰がなかったという逸話は、今から17年半も昔の2006年のことである。
しかし、2024年現在、サッカーというスポーツは(好むと好まざるとにかかわらず)アップデートしている。
すなわち、GPSやAIなどを使った膨大なデータの集積と科学的な分析。ドローンを使ったフォーメーションの練習など高度に統制された戦術。そればかりか「個の力」に頼っていた最後の崩し方すら「組織的、戦術的」に練習する。
試合中はピッチを俯瞰したスタッフがフォーメーションを絶えず観察、状況に応じてスタッフが無線で連絡しあい、それによって選手たちは柔軟にそれを変更する。……等々。
もはや、ピッチ上の選手たちだけで出来るゲームではなくなっているのだ、サッカーは。
選手だけでサッカーをしていると、それこそ「考えすぎて頭がパンクする」のである。
選手だけでサッカーをしていると、それこそ「考えすぎて頭がパンクする」のである。
三笘薫、堂安律、久保建英、遠藤航、冨安健洋、守田英正……等々(順不同)、日本代表選手の「個の力」も2006年当時から大幅に向上した。結局、森保ジャパンの活躍は選手たちの「個の力」に頼ったところが大きかったのではないか? ……とまで言われている。
その「個の力」をチームの力にまとめきれないのは、やはりベンチ(監督)の責任ではないのか? ……と。
田嶋幸三会長が『「言語技術」が日本のサッカーを変える』の中で称揚した逸話は、昔の日本プロ野球で二日酔いで猛打賞をとったスラッガーを讃える武勇伝と同じ類のアナクロニズムである。<2>
森保ジャパンの予想外の不振と敗退に、ジーコ・ジャパンの(そして平尾ジャパンの)亡霊を見てしまった気がする。
†
続きを読む