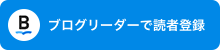▼前回のおさらい「昔のラグビー~選手はプロはNGでアマチュアでなければならなかった」(2023年10月01日)https://gazinsai.blog.jp/archives/50167186.html
アマチュアリズムを墨守していたラグビー(ラグビーユニオン)では、そのため試合中も選手たちに振る舞いは抑制的でなければならないという不文律があった。
だから、ラグビー選手たちは試合中にトライやゴールをしても喜びの表現、つまりサッカーで言う「ゴールセレブレーション」に相当する行為をしてはいけなかった。トライやゴールをしても表情ひとつ変えずに自陣に戻り、次のキックオフに備えていた。
むしろ、そのことを「美学」にしていた。ラグビー評論家・中尾亘孝はそのデビュー作『おいしいラグビーのいただきかた』(1989年)の中で、抑制的な振る舞い「トライの美学」について、内外のラガーマンの言葉を紹介している。<1>
- トライして喜びをかみしめる抑えた姿が〔ラグビーの〕いいところなんだ。(金野滋)
- トライっていうのは、ノーサイドの笛を聞いて、ドレッシング・ルームに戻ってから、ジワジワとこみ上げてくるものなんだ。(G・デイヴィス/『BRUTUS』1982年12月1日号)
中尾亘孝『おいしいラグビーのいただきかた』(1989年)19頁
こうしたラグビー(ラグビーユニオン)の習慣は、サッカーの習慣とは対照的である。ラグビー関係者の中には、その「美学」を盾にサッカーのやり方を否定する人が出てくる。
ラグビーファンで有名だった、また草ラグビーのプレーヤーでもあった小説家の野坂昭如(故人)が大のサッカー嫌いだった。
- 参照:相川藍「『作家・文学者のみたワールドカップ』野坂昭如・高橋源一郎・星野智幸・野崎歓・関川夏央・藤野千夜ほか/文學界2002年8月号」(2002.07.09)https://www.lyricnet.jp/kurushiihodosuki/2002/07/09/983/
ゴールした後、派手なガッツポーズで抱き合い喜ぶサッカー(ゴールセレブレーション)は醜くて、トライの後、表情ひとつ変えずに黙って自陣に引き上げるラグビーこそ美しい……と、野坂昭如は言うのである。
もっとも、英国人の立ち振る舞いは、イタリアや南米等と比べてもともと抑制的なもので、英国のサッカー界でも感情を抑制することを良しとし、ゴールセレブレーションの類には否定的であった。
しかし、イタリアなどラテン系の国々の選手がゴールセレブレーションをすることに影響されて、英国でもゴールセレブレーションは受け入れられ、当たり前のことになっている。それが自然なことだからだ……。
……と、デズモンド・モリスの『サッカー人間学』(1983年,原題:The Soccer Tribe)には書かれている。<2>
ラグビーでは、ラテン系諸国の習慣が英国圏ラグビー国に影響を与えることはなかった。
1991年の第2回ラグビーワールドカップ(英国,アイルランド,フランスで共同開催)に出場したアルゼンチン代表「ロス・プーマス」(Los Pumas)の選手たちは、トライした後、ゴールセレブレーション(トライセレブレーション?)をしていた。
この時は、まだ国際ラグビーフットボール評議会(IRFB,現在のワールドラグビー)のアマチュア規定が生きていた当時でもあるし、ロス・プーマスの選手たちの振る舞いは少し意外なことに思えた。この辺はラテンアメリカらしい、あるいはサッカー強国らしい行為だなとも考えた。
得点した喜びを表現しないことをもって良しとするラグビー界の「美学」も、1995年にIRFBのアマチュア規定を撤廃するとしだいに変わっていき、素直に喜びを表現するようになっていった。
その文化変容を野坂昭如はどう思ったか? 伝わっていないようである。
(つづき)
▼「昔のラグビー~監督は試合中,選手たちに指示を出してはいけなかった」(2023年10月03日)https://gazinsai.blog.jp/archives/50189280.html
▼「昔のラグビー~監督は試合中,選手たちに指示を出してはいけなかった」(2023年10月03日)https://gazinsai.blog.jp/archives/50189280.html
続きを読む




![Number(ナンバー)特別増刊 桜の凱歌。 エディージャパンW杯戦記[雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61eVygQiBjL._SL160_.jpg)